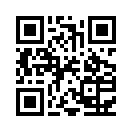2006年10月24日
ヒットラーのむすめ

「Do you know “Hitler’s daughter”?」
オーストラリア タスマニア島出身というALT(英語助手)の先生に聞いてみた。こちら、怪しげな英語交じりの日本語、彼はかなり流暢な日本語で。
「What? 何ですか?日本語の本は、大学で習ったKobo Abe とHaruki Murakamiと Junichirou Tanizakiしかわからなくて」
「いや、これはオーストラリアの作家の書いた本なんですけど。今ちょっと名前が出てこないので後で作家の名前を調べておきますね」
2004年に日本語訳が出ていて、今年までの2年間に初版第8刷まで出版されている。かなり売れている本だ。オーストラリアの文学、というか、児童文学の本は、エミリー・ロッダしか知らなかった。前述のALTの先生も、エミリー・ロッダは有名ですよ、と言っていた。
今回これを読んでみて、レベルが高いなあと正直に感じた。ストーリー運びのうまさ、登場人物の描写など感心してしまった。さくまゆみこさんの訳もいいのだと思う。
雨降りのうっとうしさ、もどかしさの中で、マーク少年がアンナの話に引きつけられていくのがとてもよく描写され、過去と現在は続いているのだという理解が深まっていくのがよく分かるのだ。読んでいるこちらの心にも、すっと落ちてくる。納得できるのだ。
平和教育にとって、過去のお話を今の子どもにわかってもらうことの難しさがあるのだが、これはその点を見事にクリアしていると思う。
架空のお話として続いてきた「ヒットラーのむすめ」が、ぐるりと回って、見せる落ちも、いい。
中学生にはぜひ、読んでほしいのだが、まだ借り手がつかない。今読書月間中のイベントとしてやっている「わたしの勧めるこの一冊」に取り上げてみよう。
Posted by hima at 19:21│Comments(2)
│本
この記事へのコメント
偶然ですが、私も最近図書館からこの本を借りて読みました。
以前から読みたい、と思いつつなかなか読めなかった本。
読み始めると一気に読んでしまった。
第二次大戦のことはもちろん、オーストラリアという国のことも
わかってとてもいい本だと思いました。
事実とは言わなくても、もしかしたらこんなこともありえたかもしれないな、
なんて思いました。
6年生へのブックトークで「アンネの日記」や「おまもり」「エリカ」など、
紹介してきましたが、ドキュメンタリーではなく物語仕立てのこの本は、
子ども達にも読みやすいのではないでしょうか。
私も来年購入しよう!
余談ですが、エミリー・ロッダって本国でも有名なのですね。
日本に入ってくるくらいだから当然でしょうが、
その国の人が言うと、改めて納得します。
以前から読みたい、と思いつつなかなか読めなかった本。
読み始めると一気に読んでしまった。
第二次大戦のことはもちろん、オーストラリアという国のことも
わかってとてもいい本だと思いました。
事実とは言わなくても、もしかしたらこんなこともありえたかもしれないな、
なんて思いました。
6年生へのブックトークで「アンネの日記」や「おまもり」「エリカ」など、
紹介してきましたが、ドキュメンタリーではなく物語仕立てのこの本は、
子ども達にも読みやすいのではないでしょうか。
私も来年購入しよう!
余談ですが、エミリー・ロッダって本国でも有名なのですね。
日本に入ってくるくらいだから当然でしょうが、
その国の人が言うと、改めて納得します。
Posted by Helenaヘレナ at 2006年10月30日 09:37
こんにちは、
Helenaさんも、『ヒットラーのむすめ』読まれたのですね。オーストラリアって知っているようで知らない国なんだなあ、とこの本を読んで思いました。移民の多い国と言うイメージはあったのですが、確かに移民の中にドイツ系の人々がいてもふしぎはないですね。
子どもたち一生懸命薦めていますが、なかなか動かなくて・・・。
Helenaさんも、『ヒットラーのむすめ』読まれたのですね。オーストラリアって知っているようで知らない国なんだなあ、とこの本を読んで思いました。移民の多い国と言うイメージはあったのですが、確かに移民の中にドイツ系の人々がいてもふしぎはないですね。
子どもたち一生懸命薦めていますが、なかなか動かなくて・・・。
Posted by hima at 2006年10月30日 21:01